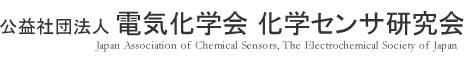化学センサの未来に向けて
化学センサ研究会・会長 松口正信
(愛媛大学大学院理工学研究科・教授)
前会長の清水陽一先生より引継ぎ、化学センサ研究会の会長を務めさせていただくことになりました。私が本会に入会したのは、1986年に故酒井義郎先生の研究室に助手として採用され、湿度センサの研究を始めたときでした。それから40年弱の間、本会には本当にお世話になってきました。このたび、歴史ある「化学センサ研究会」の会長を拝命いたしましたこと、とても光栄に感じるとともに、重責にあらためて身の引き締まる思いです。これからの2年間、お世話になった「化学センサ研究会」への恩返しのつもりで、伝統を守りつつ、さらなる発展に向けて微力を尽くしたいと思います。どうかよろしくお願い致します。
新年早々にこのご挨拶を書かせていただいているのですが、この機会に化学センサの向かう未来について考えてみました。現在、持続可能な開発目標(SDGs)やカーボンニュートラルの達成に向けたさまざまな取り組みが世界で一体となって行われています。言うまでもなく、これらの取り組みにおいて化学センサは、重要な役割を担うことが期待されます。大気汚染ガス、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの正確な濃度をモニタリングし、削減の進捗を監視することはもちろん、水素の漏えい検知や品質管理、エネルギー効率の向上や農業の持続可能性実現への貢献、健康な生活を送るための医療診断など、化学センサが必要とされる分野は今後ますます広がると思います。新しい需要に向けては、化学センサの開発にもいっそうの技術革新が必要になるでしょう。
2024年のノーベル賞は、化学賞・物理学賞ともに人工知能(AI)に関連した技術に授与されました。化学センサの開発においても、得られた多様なデータの解析はもちろん、新しいセンサ材料や構造の設計にAIを活用することでより高性能な化学センサの開発が促進されることが期待されます。一方で、AIは創造力に乏しく独自のアイデアを生み出すことが苦手だと言われています。その点、人間は過去のデータ・経験知にとらわれず、異分野・異業種の人たちとの交流を通じて知識の融合を行い、柔軟な思考で革新的な(ときには突飛とも言える)アイデアを創出できます。幸いにも本会は、産・学・官に所属する会員の方々でバランスよく構成されており、しかもお互いの顔と名前が一致するくらいの規模なので、円滑なコミュニケーションを通じて協力的な関係を築くのに適しています。今後は、新たに化学センサの導入に関心のある異分野の方々へも本会の活動を知っていただき、参加を促すことで、化学センサ研究のさらなる活性化につなげられたらと考えています。
さらに、国際連携を促進することの重要性も感じています。本会としては、これまでもIMCSやACCSを通じて積極的に国際会議に参加し、国際的なリーダーシップを発揮してまいりました。昨年11月には、久しぶりの日本開催となる第15回アジア化学センサ国際会議(ACCS2024)が北九州において開催され、大成功のうちに終わることができました。これもひとえに、清水実行委員長を始めとして、実行委員の先生方、そして参加していただいた皆様のお力のたまものと思います。私も実行委員の一人として大会運営に関わりましたが、あらためて海外研究者の開発動向の把握や連携の必要性を実感しました。私は、一昨年の11月に、韓国の物理センサも含めたセンサの国内会議に招待されて講演を行う機会を得ました。その際に、あまり国際会議に参加していない韓国の化学センサの研究者の方々とも交流を深めることができました。このように、国際学会だけでなく、化学センサ研究発表会のような国内学会でも、海外の研究者を招待しての国際交流を推進できたらと考えています。
私の任期中、会員の皆様のご意見・ご要望を伺いながら、できることから少しずつより良い方向へ進めて行きたいと考えています。ご支援とご協力をお願い申し上げます。